今回は、小さなお子様の薬の飲ませ方についてのお話です。
ミルク主体の乳児期の場合は、食事回数が多く不規則なため1日3回毎食後といわれても困ってしまいます。特に食後はお腹がいっぱいで飲めなかったり、ミルクと一緒に吐いてしまうこともあります。医師から特別な指示がない限り、食前・食後にあまりこだわらなくてもよいでしょう。
続きを読む »
お薬に「まごころ」を添えて。
ここからナビゲーション


メディカル一光の薬剤師による、お薬や健康についてのコラム。
毎月月末に更新予定です。
ここから本文
今回は、小さなお子様の薬の飲ませ方についてのお話です。
ミルク主体の乳児期の場合は、食事回数が多く不規則なため1日3回毎食後といわれても困ってしまいます。特に食後はお腹がいっぱいで飲めなかったり、ミルクと一緒に吐いてしまうこともあります。医師から特別な指示がない限り、食前・食後にあまりこだわらなくてもよいでしょう。
続きを読む »
近頃食生活の偏りを改善したり、健康の維持、増進を図る目的で「サプリメント」を利用する人が増えています。サプリメント市場は大変活発化し、錠剤 カプセル 飲料などさまざまです。
一般にサプリメントとは、「体に必要な栄養成分や、体によい効果をもたらす機能成分を補う食品」を指します。
また、サプリメントは大きく2つに分けられます。
続きを読む »
お薬の飲み方の説明で、「コップ一杯の水で飲んでくださいね」と言われたことはないでしょうか。「水なんか飲まなくっても、薬ぐらい呑み込めるよ」という方もおられるかもしれません。でも、この一杯の水が、薬の効きめや副作用に随分関係しているのです。
続きを読む »
肩こりは首すじ、首のつけ根から背部や両肩にかけてこわばり感、はった感じ、重だるい感じ、痛みなどの入り交じった不快な感覚の総称です。主観的にはきわめて苦痛を伴い、時には頭痛、悪心やめまいなどを伴います。つまり、頸部、肩甲帯、背部における筋肉の疲労・過労状態による局所痛、放散痛、関連痛などを含んでいます。
続きを読む »
患者様から「高血圧の薬とグレープフルーツジュースは一緒に飲んではいけないの?」とよく質問を受けます。確かに、飲み合わせが悪い薬はあります。高血圧の薬の中には、血圧を下げる仕組みや作用が違う薬が数種類あり、問題となる薬はその中の一部です。
続きを読む »
お薬とお薬の相互作用は患者様の関心も高いのですが、お薬と食物の相互作用については、あまり関心がない方も多く注意が必要です。今回は、喘息のお薬であるテオフィリンを例にとり、日常生活で注意すべきお薬の相互作用について、一例を紹介致します。
続きを読む »
骨は私達の体を支えたり、大切な臓器を保護するなど私達の体を様々な面でサポートしてくれています。しかし、年をとると、背中が丸くなったり、骨折を起こしやすくなります。これは骨粗鬆症によることが多いのです。
続きを読む »
なかなか血圧の下がらない患者様から「薬の種類が増えたけど何故?」という質問をよく受けます。このような場合の多くは『作用の仕方の違う薬』が追加になっています。血圧を下げる薬には様々なタイプがあり、医師はその中から相性のよい薬を選んでいます。今回は代表的な高血圧の薬をタイプ別に紹介します。
続きを読む »
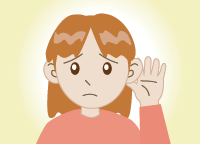
難聴とは耳が聞こえにくくなることですが、聴力検査においては、ある一定以上の音がきこえない、あるいは聞こえにくい状態をいいます。音は耳を通して脳で認識されますが、その経路においていずれかの箇所に障害が起きても難聴になってしまいます。音を伝える部分に障害がある場合を「伝音難聴」といい、音を感じる部分に障害がある場合を「感音難聴」といいます。
続きを読む »
お子様が熱を出されると戸惑う方が多いと思いますが、落ち着いて様子を観察し、次のような対応をしてあげて下さい。
熱が上がりかけの時は寒気がして震えたりします。この時は温かくしてあげて下さい。逆に熱が上がりきると汗が出て暑がります。濡れた下着などは取替え、寒がらない程度に薄着にしてあげて下さい。また、発熱時には脱水症状になりやすいので、小まめな水分摂取も大切です。高熱が出ると脳に障害が出るのではないかと心配になりますが、40度近い高熱でも障害が起こることはないと言われています。
続きを読む »
憂鬱な梅雨の季節も過ぎ、いよいよ夏本番。楽しいイベントを控えている方も多いのではないでしょうか。しかしこの時期、「熱中症」で病院に運ばれる方のニュースをテレビや新聞で見る機会が増えます。熱中症はスポーツ活動中や高温環境での労働など比較的若い世代に起こると思われがちですが、高齢者でも例外ではありません。今回は、夏に多い熱中症についてのお話です。
続きを読む »
夏が近づいてくると テレビでも話題になりますよね。食中毒。飲食店でばかり起こっているようですが、その内20%は家庭で起こっています。夏場だけでなく年間通して100件以上の報告があり、特に7月~9月で倍の200件近くの報告が上がっているのです。大好きな環境が 高温多湿(25℃以上・湿度70%以上)ですので納得です。また、人は高温多湿の環境では抵抗力が低下しやすいのでさらに悪循環となります。
続きを読む »
皆さんは医師や薬剤師から「続けて服用している薬はありますか?」と聞かれて薬の名前を正確に答えることができますか?何種類も服用していると薬の名前までは答えられないのではないでしょうか。
新潟中越地震でも、いつも飲んでいる薬がわからず、困られた方がたくさんおられたそうです。高血圧や糖尿病など慢性疾患をお持ちの方は、災害時でも薬は飲み続けなければいけませんが、かかりつけの病院や薬局が利用できるとは限りませんし、救援に来た医師や薬剤師も短期間で入れ替わります。そんな時に役立つのが薬の記録簿である「お薬手帳」です。
続きを読む »
夜、なかなか寝付かれなくて苦しい思いをしたことはありませんか。
日本では成人の約5人に1人が不眠に悩んでいるといわれています。原因の一つとして、生活リズムの乱れによる体内時計のズレがあげられます。朝起きて太陽の光を浴びると、体内時計が時を刻み始め、14~16時間たつと、眠りを誘うホルモン「メラトニン」が分泌されて眠気がおこります。毎朝きちんと起き陽光を浴びていれば、寝付きは良いものです。また夜はゆったりとした気分で自然に眠気を待つことも大切です。
続きを読む »
この季節になると気になり始めるのが汗、それにともなう体臭・・・耳が痛い話ですねぇ
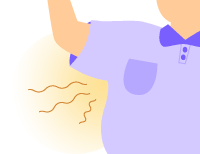
汗は体臭の一番の原因といわれています。汗をかくと老廃物が皮膚や汗腺に溜まり、雑菌が繁殖する。それが、体臭の原因となります。特に運動不足の体では、雑菌繁殖のしやすい汗の状態になることになり、汗の臭いを発生するということにもつながるといわれています。
続きを読む »
打撲や腰痛の時、一度はお世話になったことのある薬といえば、シップ剤ではないでしょうか。
シップ剤は大きく分けると冷シップと温シップがあります。一般的に捻挫や打撲など、熱を持っている患部に貼るのは冷シップ、慢性的な腰痛や肩こりなどには、温シップを使います。温シップにはトウガラシ成分が入っているものもあり、これが血管を拡張させ血行改善作用を促進します。
続きを読む »
水虫とは、白癬菌という真菌の一種が足に感染した状態のことをいいます。真菌とは人の身近にある「カビ」の一種です。
カビの仲間には、良いことをするカビと、悪いことをするカビがあります。人にとって有益なカビは納豆やヨーグルトなどの発酵食品を作り、人体に害のあるカビは、食べると食中毒をおこしたり、ハウスダストの原因になったりします。真菌類の一つ、ビール酵母はビール醸造に欠かせない有益な真菌ですが、白癬菌の方は感染すると水虫になってしまう厄介な真菌です。
続きを読む »
ある調査によると、うがい薬を使用される方の多くは含嗽液が適切な濃度よりも3~6倍薄く、しかもうがい時間が短すぎるため、薬剤の殺菌作用を十分発揮できていないことが指摘されています。個々の薬剤の適正な希釈濃度を確認してうがいしましょう。
続きを読む »
若い頃には美肌であっても、加齢とともに皮膚の老化現象が始まってきます。紫外線、大気汚染、食生活、ストレスなど、現代社会では影響を与える要因がたくさん存在します。肌を健康に美しく保つためにはスキンケアも大切ですが、ここでは食事と栄養についてお話します。
続きを読む »
動脈硬化の原因としては、コレステロールがよく知られていますが、実は、血液中の「中性脂肪」も動脈硬化に深くかかわっていることが、近年の研究で明らかになってきました。
血液中には、色々な種類の脂質が含まれています。健康診断などで、よく耳にする「コレステロール」や、「中性脂肪」もその1つです。コレステロールは細胞の膜やホルモンなどの材料になるものです。これに対し中性脂肪は、体を動かすエネルギー源になります。
中性脂肪は、食べ物に含まれる脂質をもとに、小腸で作られるほか、肝臓でも、脂質や糖質などから合成されます。そして、血液に入って全身をめぐり、エネルギー源として、使用されます。また、全身の脂肪細胞に蓄えられ、必要に応じてエネルギーに変えられます。
コレステロールや中性脂肪はほとんどが水分である血液に溶け込むことができません。そのため、特殊なたんぱく質と結合した「リポたんぱく」という形で、血液中に存在しています。
続きを読む »