アトピー性皮膚炎とは?

アトピー性皮膚炎は、皮膚炎を起こしやすい体質的な素因を持った人に、ストレスやダニ・ほこりなどの悪化させる要素が加わることで発症する病気です。主な症状は強いかゆみを伴う、赤くブツブツとした湿疹で、よくなったり悪くなったりを繰り返します。
症状の現れやすい部位は年代によって異なりますが、一般に多くできる部位は、顔(目、耳、口の周りなど)や関節部(肘の内側や膝の裏側のしわの部分)です。
続きを読む »
お薬に「まごころ」を添えて。
ここからナビゲーション


メディカル一光の薬剤師による、お薬や健康についてのコラム。
毎月月末に更新予定です。
ここから本文

アトピー性皮膚炎は、皮膚炎を起こしやすい体質的な素因を持った人に、ストレスやダニ・ほこりなどの悪化させる要素が加わることで発症する病気です。主な症状は強いかゆみを伴う、赤くブツブツとした湿疹で、よくなったり悪くなったりを繰り返します。
症状の現れやすい部位は年代によって異なりますが、一般に多くできる部位は、顔(目、耳、口の周りなど)や関節部(肘の内側や膝の裏側のしわの部分)です。
続きを読む »
「えーっと、あの人誰だったかな?」と年を重ねると増える物忘れ。これは、脳の神経細胞の減少という老化現象で、誰にでも起こります。一方、認知症は、神経細胞の消失が早く、記憶力、判断力に障害が起こり、妄想などの精神症状を伴う脳の病気です。認知症は「アルツハイマー病」と「脳血管障害」に分けられ、患者さんは2005年度には約189万人に達しています。
続きを読む »
喘息は気道が狭くなって呼吸が苦しくなる「喘息発作」を繰り返す病気です。
発作が起きると、呼吸に伴って「ゼーゼー、ヒューヒュー」と音がします。
これは喘息の典型的な症状で「喘鳴」と呼ばれます。発作が、ひどくなると、呼吸困難になり、命にかかわることもあります。
発作が治まると呼吸は楽になりますが、発作が治まっているときでも、気道には慢性的な炎症が起こっています。常に炎症が起こっているため、気道が過敏になり、わずかな刺激が加わっただけでも、発作が起こるのです。
続きを読む »
古くから疲れた時にはすっぱい物を食べると良いといわれていますが、昔の人は経験的にすっぱいもの(クエン酸)には疲労回復効果があることを知っていたようです。
クエン酸は、レモンなど柑橘類、梅干し、お酢などに含まれている酸味成分です。
クエン酸には、疲労回復効果やカルシウムの吸収を促進する作用があり、最近では血液をサラサラにする効果も注目されています。
続きを読む »
みなさん、ステロイド薬というと、効き目が強いが副作用も強い薬と感じておられる方が多いのではないでしょうか。
ステロイド薬は膠原病、炎症性疾患、アレルギー疾患、ネフローゼ症候群など様々な治療に用いられる効果の高いお薬です。また満月様顔貌(顔が丸くなる)や糖尿病、骨粗鬆症など多くの副作用が知られています。その意味ではこの薬は作用が強く、副作用も多い薬といえますが、副作用の多くは、一時的な減量や予防薬との併用で最小限にとどめることが可能です。
続きを読む »
ADHDという言葉をお聞きになったことはあるでしょうか?
ADHD=Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder・・・「注意欠陥多動性障害」という発達障害の1つです。発達障害には自閉症、LD(学習障害)などがあります。どれも親にとっては病気と考えられず、単なる子供のわがまま、怠慢、勉強嫌いと思い込んでしまい、厳しく叱ったり、世間体を気に病み悲観したり、ついつい子供に矛先を向けてしまいます。
続きを読む »
じめじめ蒸し暑い季節がやってきました。そんな環境を水虫は一番好みます。水虫の正体は白癬菌(はくせんきん)というカビの一種で、症状は大きく3つの型に分かれます。
“風が吹いても痛い”といわれている”痛風”。
その発作の原因は「尿酸」です。血液中に尿酸が過剰に増加すると、尿酸の結晶が関節にたまり炎症を引き起こします。日本では1960年代の高度経済成長期以降、食生活の欧米化で脂肪や動物性のたんぱく質の多い食事が普及してきた頃から急増し、今では代表的な生活習慣病の一つとなりました。
続きを読む »
便秘の定義は、『3日以上排便がなく、不快な状態が続いて日常生活に支障がある場合』としています。
一般的には食事や年齢、体質などが原因で起こる慢性の便秘が多く、特に高齢の方は腸の動きが鈍くなって便秘になりがちです。また女性はホルモンや腹筋が弱いなどの理由に加え、ダイエットや排便を我慢することも原因の一つです。
続きを読む »
健康診断の検査項目には必ず総コレステロールと中性脂肪があります。体内の脂肪の量が増えすぎると動脈硬化になりやすく、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす可能性があることは、よくご存知のことと思います。食事療法や運動療法でコントロールするのが最良ですが、改善できない場合は薬で下げる必要があります。
続きを読む »
メタボリックシンドロームとは、動脈硬化の危険因子(肥満、高脂血症、高血糖、高血圧)を複数併せもった状態です。なぜ起きるのでしょうか?
おなかの周りにたまった「内臓脂肪」が大きな原因です。内臓脂肪が過剰にたまるとアディポサイトカイン(脂肪から分泌される体のさまざまな機能を調節する物質)の分泌に異常が生じ、高脂血症や高血糖、高血圧などを引き起こします。こうした状態が続くと動脈硬化が進み、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞などの病気を起こす危険が高まっていきます。
続きを読む »
血圧とは血液が血管の内壁を押す力のことで、高血圧症とは血圧を1~数週間測定しても正常よりも高い状態のときを言います。
病院などで高血圧症といわれるのは最高血圧が140mmHg以上、または、最低血圧が90mmHg以上のときです。
(高血圧治療ガイドラインでは高血圧を表1“成人における血圧値の分類”のように分類しています。また、すべての高血圧に対して表2 “生活習慣の修正”を推奨しています。)
続きを読む »
足の指が腫れてひどく痛む痛風。この病気の原因になっているのが体内のエネルギーの燃えカスである尿酸です。
私たち薬剤師は、尿酸値が高く治療を必要と判断された患者様にお薬を渡す際に、「体の中の尿酸を下げる薬です」と一口で説明してしまいがちですが、尿酸を下げるお薬には大きく分けて2種類あります。
続きを読む »
「この薬、副作用の心配はありませんか?」と患者様から聞かれることがあります。副作用のない薬はあるかと言えば、答えは「ノー」です。程度に差はあるにせよ全く副作用の無い薬はありません。
続きを読む »
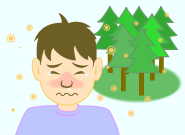
「花粉症」はアレルギー性疾患の一つで、花粉が体内に入ることでおこるアレルギー反応が原因です。「くしゃみ、鼻水、鼻詰まり」そして「目のかゆみ、なみだ目」など鼻や目の症状が主ですが、さらに皮膚や発熱などの全身症状も伴うこともあります。
このように、異物を排除しようとする「免疫」の働きが体に都合の悪い症状を起こすことを「アレルギー」といいます。
花粉が主な原因となるアレルギー性疾患の中でも、最も多いものはスギ花粉症で2~4月ごろに症状がおきます。スギの次が3~5月ごろにおきるヒノキ花粉症です。
続きを読む »
「小さい頃におたふく風邪にかかったことある?」と聞かれ「うん、かかったことある」と返答すると「じゃあ、もう免疫あるから大丈夫だね」というような会話を聞かれたことがあると思います。
そう私達の体には、一度かかった病気に対する抵抗力が生まれているのです。私達の周りには様々な細菌やウイルスが生息していますが、私達が元気で過ごしていられるのはそれらに対する抵抗力が備わっているからです。それが免疫力です。
続きを読む »
血を固まりにくくする”ワーファリン”というお薬をご存知ですか?今回はワーファリンと飲食物の関係についてお話します。
このお薬を飲まれている方は「納豆とクロレラは食べないこと」と医師・薬剤師から指導を受けられていると思います。それはなぜでしょうか。
その答えの鍵は”ビタミンK”という栄養素にあります。 続きを読む »
皮膚科で処方されるステロイドなどの軟膏やクリーム。整形外科で処方される痛み止めの軟膏など、軟膏やクリームにもいろんな種類の塗り薬があります。目的にあった使い方をしないと効き目が落ちたり、副作用が出やすくなったりします。今回は、塗り薬の使い方についてのお話です。
続きを読む »
一時期大ブームを巻き起こしたアロマテラピー。その後も消え去ること無くひそかなブームは続いています。使ってみたいけど、どのようにして使えばよいのか?と思われていた方に簡単な使い方をご紹介いたします。
続きを読む »
寒い季節がやってきました。仕事等の疲れも、寒さで増してくるこの季節。正しい入浴方法で、疲労回復して心身ともにリフレッシュしましょう。
冬場には寒いからといって、ついつい熱いお風呂に入りがちになります。しかし、熱いお風呂は、入ったときに血圧がぐっと上がるため、体に負担がかかってしまいます。お湯が熱くないと体が温まらないと思うかもしれませんが、逆に血管が拡張してしまい、血液の流れが悪くなって体が温まりません。また、大量の汗をかいてしまうので、体から水分が抜けて血液がドロドロになってしまう原因にもなり、ますます血流が悪くなってしまいます。
続きを読む »